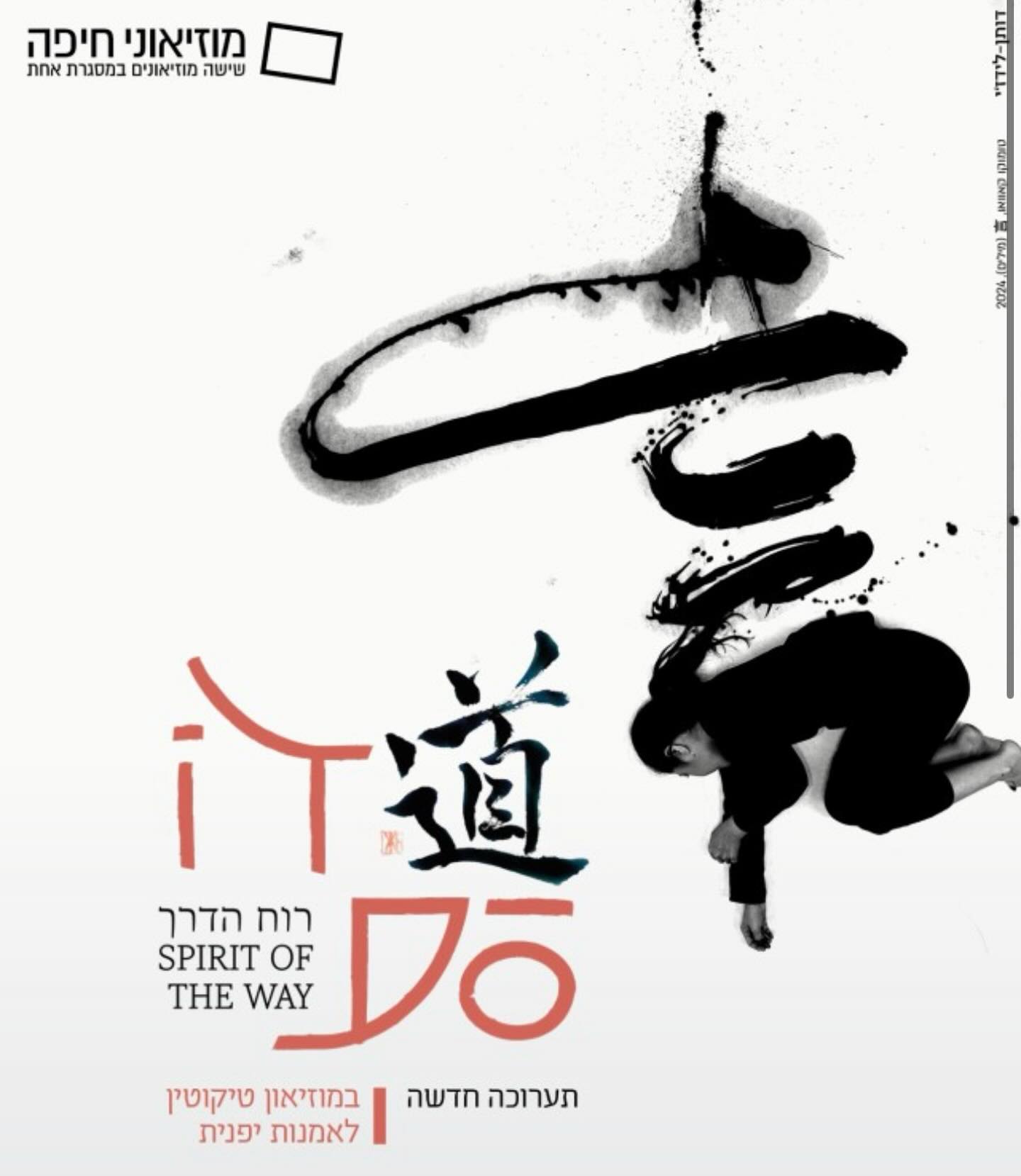『呼び出し先生タナカ』にて「鬼滅の漢字」がTV放送されました
2026.01.21
1月19日(月)19:00~放送されたフジテレビ系列『#呼び出し先生タナカ』芸能界漢字王決定戦において、
昨年7月に北野天満宮 @kitano_tenmangu にて行われた”鬼滅の刃”と”日本漢字能力検定協会”のコラボ企画「鬼滅の漢字」の揮毫の場面を少し取り上げていただきました。
日本漢字能力検定協会 @kanken_official_ig 全面協力のスペシャル回、漢字の勉強になりましたし、鬼滅の刃や京都の問題も出てきますので是非ご覧ください〜。
TVerでご覧いただけます。